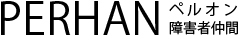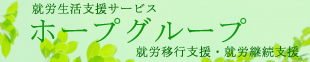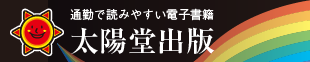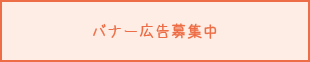2024年7月19日更新

-
子どもの発達の話と、人と人をつなぐ場所「テテトコ」アプリとは?ディレクターに聴いてみよう⁉ (1/3)
今回は、新しくできた、「テテトコ」アプリの特集です。どんなことができて、どんな思いで作られたのでしょうか?ディレクターを務める大曽根さんと、真喜志さんにインタビューしてみました。(注:2024年2月にインタビューを行いました。2024年6月からアプリのリリース開始です。公式サイトはこちら)

携帯でデモ画面を見せてくださる大曽根さん(奥)と資料を調べてくださる真喜志さん(手前)。
―自己紹介とテテトコとのかかわり―
記者A.ではまずは簡単にお名前と出身地、アピールできるポイントとかあればお聞かせください。また、普段どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、今回のアプリ『テテトコ』との関わりについてもお話をお聞きできればと思います。
大曽根.我々は今、株式会社ZIZOっていう所で、働いていまして、広告制作、ウェブサイトの制作、広告のマーケティングを受託で制作している会社です。その会社で、僕はディレクターとして働いています。例えば「ウェブサイトで問い合わせが少ないんだけどどうしよう」みたいなお問い合わせをいただいたら、そのウェブサイトを改善したり、そのウェブでの戦略設計を一緒に考えたり、そういったところの仕事をさせていただいています。
『テテトコ』ではこちらの真喜志と二人で、プロジェクトを進めています。
真喜志.僕も大曽根と一緒で、職種としてはウェブディレクターになるんですけども、ウェブディレクターといっても幅が広くて、デザイナーさんとかプログラマーさんに「こうやって作って行きましょう」って進行管理みたいなことをする仕事もありますし、先ほどの大曽根が言った通り、例えばその数字のデータをちょっと分析して「ウェブサイトが今こういう状況だからこうしていこう」っていう戦略設計みたいなことをすることもあります。また、結構ライターとして文章を書く仕事をやっていたので、そういうこともディレクターとして働きながらしています。
『テテトコ』では、大曽根と一緒に、最初は「こういうアプリ作りたいなぁ」と思いつくところから実際それを形にしてくところまで関わっています。僕らと別にデザイナーとかエンジニア、プログラマーの人達がいるんですけど、その人たちといっしょに、見た目どういう物で、どういう機能を作って、どういう広告の出し方をしてという、僕らがプロジェクト自体をマネジメントする働き方もしています。
―自分の子どもの発達特性と似ている人同志が繋がりやすいSNSアプリ―
記者A.お話し頂きました『テテトコ』なんですけども、どんなアプリなのかっていうことをお聞きしたいのと、もし可能でしたらその使命というか、どういうのをやろうとして作られたのかみたいなことなどをお伝え頂ければありがたいなと思います。
大曽根.目指してるビジョンは、「子どもの発達の話しを、もっと気軽に当たり前に」っていうところを掲げていて、アプリは、「自分の子どもの発達特性と似ている人同志が繋がりやすいSNSアプリ」になります。普通の子育ての話みたいに、そういう発達特性に関わる話しを、もっと気軽にできるような世の中になったらいいなってそういうところを目指してやっています。
記者A.ありがとうございます。
―自分と同じ立場の人達と安心して同じ気持ちでフラットに話せる場所を作りたい―
大曽根.メインのターゲットは発達特性に悩まれているお子さんがいらっしゃる親御さんです。
記者A.親御さんが使うアプリなんですね。
真喜志.「子どもの発達に関する話がなかなかちょっと言いだしづらい」っていうのが多分あるのかなと思ってて、それは診断がついていようが、グレーゾーンの子どもの親であろうが、普通に保育園、小学校とかに行かれてて、ぱっとママ友に「うちの子って…」って言うのはちょっとまだ難しかったりもするのかなぁと思っています。孤独な気持ちを持ってたりとかするのかなぁとか…。「本当はもっと普通に子どもの話をみんなとしたいねんけどな」って気持ちがあるのじゃないかなぁって我々は思っています。
そこを繋ぐ場所、たとえば親の会みたいなものが、リアルでは、あったりはすると思うんですけれども、オンラインで、全国の人と繋がれるようなものがあってもいいのでは、親御さんが「本当に安心して自分と同じ立場の人達と同じ気持ちでフラットに話せる場所」って言うのを作りたいなぁと思って作ったのが、この『テテトコ』最初の存在意義みたいな、きっかけかなと思います。
―「ZIZO」さんと「テテトコ」さんの名前の由来―
記者A.ありがとうございます。では、御社のお名前とかアプリの名前とか、その「ZIZO」さんだったり、『テテトコ』さんだったりとか、独特な印象を受けるのですけれども、申し訳ないかもしれないですが、どんな経緯でどこから来てるのかな~とか、お名前にまつわるお話しをお聞きできればありがたいのですが。(一同 ほほ笑み)
大曽根.社名に関しては、創業者というか社長が二人いて、その二人がなんとなくその、お地蔵さんにほぼ顔が似てるから「ZIZO」にしたと聞いてます(一同 ほほ笑み)。社名ってそんな簡単に決めるんや、そんな理由で決めるんだ…と思いましたけど(ほほ笑み)。
『テテトコ』という名前は、結構いろいろ考えて悩んでつけました。当て字するとしたら、handの手と手の複数の系で「手々」そして子どもの「子」。さっき言ったようにこのアプリって、「発達特性に悩んでる親御さん達を繋ぐ」って意味があるので、そういうイメージから「手」っていうところと、その子どもっていう所で、後はまぁなんか語感というか響きとか覚えてもらいやすさとか、いろんな所をちょっと検討させていただいて、この名前にしたっていう感じです。
記者A.なるほど。なんか謎が解けたみたいで嬉しいです。
―横のつながりが作りづらい世の中なら、つながりやすいアプリを作ってしまいたい―
記者A.次ですが、お話頂ける範囲内で結構ですので、アプリ「テテトコ」はどのような事が起こって、さっきも少しお話いただきましたが、きっかけや転機とか、そういったところのお話を伺ってみたいです。
大曽根.私の知人や親戚の子どもさんで発達特性がゆっくりな子どもさんがいらっしゃって、小さい時から児童発達支援の施設に通所されていて、やはり色々、自分の子どもさんの特性にあった情報や経験談が見つけづらかったり、横のつながりが作りづらかったりというところがあったらしく・・・。
真喜志.チームの中に何人か発達特性がゆっくりな、子どもさんを育てている親御さんっていう方々がいらっしゃっていて、でまぁ、さっき言ったみたいに横のつながりがないって所が浮き彫りになってきて、そこを何とかしたいなぁと思ったのが、「最初のアイデアのきっかけになった」と思ってます。
ペルオンとは?
ペルオンはホープグループ、ミッション株式会社を母体にしたペルオン実行委員会が制作してるポータルサイトです。
障害の当事者が作る当事者目線のサイトが作れないかと思い、サイトを立ち上げました。ペルオンという名前はPersonnes handicapées(ペルソンヌ・オンディキャピー)の略で、障害者仲間という意味からとりました。
当事者会・支援団体・家族・地域・職業・年齢などの枠を超えて、障害者に関係する全ての人が連携して、さまざまなことにチャレンジし、障害者の可能性を探ってまいります!
ペルオンに興味を持ったあなた!もうすでに、仲間なんです。

- トピックの分類

- 精神障害の仲間

- 発達障害の仲間

- 知的障害の仲間

- 身体障害の仲間

- その他の仲間

- 当事者

- 家族

- 支援者

- 医療従事者

- 研究者
●「障害」の表記について
当サイトでは、「障がい者」を「障害者」と表記しています。
「障がい者」という表記の場合、音声ブラウザやスクリーン・リーダー等で読み上げる際、「さわりがいもの」と読み上げられてしまう場合あります。そのため、「障害者」という表記で統一をしています。
メルマガでいち早く、更新をご案内します。ご希望の方はメールフォームにてお申し込み願います。
広告